・機械オペレーター
・生産管理
・外勤営業
・インサイドセールス
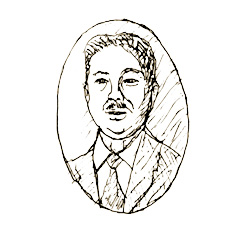
田島志一

田島志一が日本橋町に設立した日本紙器製造所社屋
日本紙業発展に一役買ったのが「紙器」という言葉である。「紙器」は、日常的には聞きなれない言葉だが、紙箱だけではなく、紙加工製品全般を表す言葉として古くから使われ、業界内では、定着している。明治末年、それまで紙箱ないし紙函と呼ばれていたものを、「紙器」とネーミングしたのは、日本紙業の歴史に度々登場する田島志一である。田島は明治44年(1910)5月、ロンドンで行われた日英博覧会へ出かけ、そこでもろもろの紙加工製品に接し、それらがペーパー・ウエア(紙製品)と呼ばれていることを知った。田島はそれらに紙器という訳語をつけ、後にみずからもそれを工場名に冠した。明治45年に日本橋区本町に設立した日本紙器製造所(日本紙業の前身)がそれである。紙器は紙箱より広く板紙加工製品を総称した名称で、実態をよりよく表現している。現在紙器に当たる英語名には、paper wareのほか、パーパー・コンテナー(paper container=ダンボール製大箱をさす)や、ドイツ語のカルトン(Karton)からきたカートン(Carton)があり、ちなみに最もポピュラーな紙器製品である折りたたみ箱はフォールディング・カートン「folding carton」と呼ばれている。ちなみに瓶入り牛乳を駆逐しつつある紙箱入り牛乳はミルク・カートンである。

日本初の国産石鹸。
当時のラベルやパッケージそのままで、復刻したもの。
紙業発展の黎明期に最初の主役を演じたのは、大阪であった。明治11年(1878)、納屋伊平が大阪東区道修町の田辺五兵衛商店(現田辺製薬)から重炭酸ソーダ1ポンド入れ紙箱100個の注文をうけたのが、薬品容器としての紙箱量産化の第一歩だった。原料は輸入ボール紙と上張り用の艶紙で、いかにも“洋箱”らしいものが国産化された。明治13年になると、この納谷紙函製造所(現納谷紙器工業所)のほかに、西区江戸堀南通で松田潤吉が、菱形・六角形の色紙で装飾された白粉箱の製造販売を始め、北区東梅ヶ枝町の高田芳兵衛が玩具用化粧箱をつくり出した。明治14~15年になると、薬品・化粧品のほかにメリヤス・石鹸・洋傘・帽子など新時代の商品が勃興期に入り、これに必要な紙箱需要も急増し、大阪で30数名の同業者が簇生するに至った。
東京では納谷の開業におくれることほぼ一年の明治7年(1874)、もと信州上田藩士、本郷追分町の原沢という丸薬製造屋が、下谷の同業者でもと松前藩士の井上直之丞と談笑中に、たまたま店にきた紙屑屋が持っていた舶来のボール箱をみて買い求め、これを見本に丸薬用の容器をつくり出したのが東京での紙器製造のはしりである。工具は包丁・押し切り鋏・文回し(コンパス)・鍛造子鋏・ものさしなどだった。明治14年、日本橋の紙問屋スワラヤ商店に舶来の鼠色ボール紙が入荷し、井上直之丞はこれを買い、紙箱製造を始めた。このころ東京でも新産業の勃興期で、既存の菓子・鶏卵・海苔などのほか、石鹸・メリヤス向けの紙箱需要が急増した。その後、隅田川を挟んだ下谷・浅草・本所・深川方面に、陸続きとして紙器製造業者が開業した。大阪では、年ごとに同業者の数がふえ、明治24~5年ごろには、紙箱製造業者の総計は120名余、職工は350人に及んだ。当時使われた板紙の多くは輸入品で、年間消費量は東京方面で約200トン、大阪方面で500トン、紙箱の生産金額は約45万円に達した。(『全国紙器工業会史』より)

大正11年ごろ使われていたビクトリア型印刷機(墨田区東京都慰霊堂境内に展示)
ハードの主役は、紙業の歴史の中に途切れることなく登場する名機、ビクトリア印刷機である。ビクトリア型の平圧印刷機は、1887年(明治29)のドイツのシュナイダー社が製造販売したもので、従来の平圧印刷機よりも強圧が印刷盤面にかかる画期的な機械であった。ビクトリア型の登場が従来の平圧機の改良競争にとどめをさしたといっていい。ドイツ製の機械にビクトリアという英名を冠したのは、偉大なビクトリア女王にあやかったといわれる。以後、わが国の印刷業界が大判印刷機・高速輪転機・オフセット多色刷り印刷機などをあいついで導入し、大型化・高級化を進めていったなかでも、小回りのきく付帯設備として、このビクトリア型は絶えず利用され続けた。明治39年6月18日現在、凸版印刷合資会社の主要設備一覧をみると、印刷機械は凸版46全判6台・同菊全判10台・活版菊全判5台・石版46半截判2台に交じり、ビクトリア468截判2台と記されている。『凸版印刷六十年史』(昭和35年刊)。
わが国にボール紙が初めて輸入されたのは明治4年(「神奈川県紙函工業組合沿革史」)。それでどんな紙函をどんな方法でつくったのかは不明だが、『全国紙器工業会史』はこう書いている。「その頃の製函技術ははなはだ幼稚なもので、原紙をきるには鋏を用い、角切りには罫引き台に紙をのせ、大工用の罫引きで筋を入れ、鋏で四隅を切りとるなど、紙函100個を仕上げるのに、三人の職工が終日働いて4日間を費やした」。明治6年、大阪堺に納屋伊平(1831~?)という人物がいた。長男が小学校入学期を迎えたとき、伊平は、息子のために学用品入れをつくった。古い和装書籍の青表紙をほぐし、これを芯にして紙箱をつくった。この鞄をみて、学友たちがほしがり、あちこちから頼まれるようになり、伊平は商売として、鞄を作り、夜店の商人に売らせることにした。明治8年6月、伊兵四四歳、自家の軒先に看板をかかげ、伊平は本格的に製函業にのり出した。紙箱製造の誕生である。
手探りで始まった日本の紙業に命を吹き込んだのが、日本の近代紙器業のパイオニア田島志一である。田島は、大正3年(1924)に52歳で不遇のうちに亡くなったが、その波乱に富んだ生涯は日本紙業発展の歴史の中に、本流といえる足跡を刻んでいる。田島を紙業発展の主役に押し上げるきっかけとなったのが、明治も終わりに近い43年(1910)、ロンドンで開催された英博覧会である。田島は、真美大観や古美術品をたずさえ、日本の美術印刷や木版コロタイプの紹介をかねて渡欧した。彼はそこで、紙箱以外に、紙皿・紙盆・紙コップ・煙草函・装身具や貴金属容器・商品宣伝用スタンドなど、板紙がさまざまな用途に加工・使用されている実態を見、今後、日本紙業界も、紙製品加工業が発展するだろうという確信を得た。帰途、彼は米国滞在中、トムソン型打抜機などの機械や器具類の輸入契約をし、帰国した。そして明治45年1月、日本銀行に近い日本橋本町2番地の裏通りで個人経営の「日本紙器製造所」を起こした。これが現在の「日本紙業株式会社」の起こりである。

田島志一が明治45年に設立した日本紙器製造所社屋
田島の日本紙器製造所の規模は、最初は敷地20坪に男女従業員25名、トムソン型打抜機2、断裁機1のほか、折曲機、角切機、箱止機を備え、それでも当時としては大きな紙器工場であった。しかし、企業の多角化を目指していた彼は、先立つものは資金、個人経営より会社組織、まず他人資本を導入することが先決と考えた。実際には、設備を大型化しなければ、注文をこなしきれないという現実問題もあった。大正2年(1913)8月、「日本紙器製造株式会社」を資本金50万円で創立、社長に政治家で東京商工会議所会頭、星野錫を迎え、専務に田島志一、常務に元中外商業新聞社広告部長の酒田啓次郎を就任させた。星野の顔で、資本金50万円という当時としては日本最大の紙器会社が誕生したわけである。会社は順調に推移しさらに大正3年7月、第一次世界大戦が勃発、戦争は、わが国に空前絶後の好況をもたらした。 外国からの原料や製品の輸入は杜絶えたものの、戦火を浴びないわが国へ、外国から、あらゆる工業品の注文が殺到、米国・カナダ・中国向け輸出が爆発的にふえた。この大戦の好況で日本紙器は大正10年までに12回の増資を行い、資本金は1000万円になった。さらに大正14年(1925)、「日本紙器製造株式会社」を「日本紙業株式会社」と改め、大正7年には、東京府下亀有村(現葛飾区亀有)に亀有工場を開設、板紙・洋紙・段ボールなどを生産、製紙製函の一貫メーカーにのしあがった。当時亀有工場の敷地は2万3000余坪に及んだ。同8月、大阪府下鯰江村に大阪工場を設け、関西方面の紙器・印刷の需要に応じた。さらに田島は、製紙用パルプ自給計画を立て、満州のハルピンとウラジオストックの中間の海林附近に森林を買収、開発業務すべての先頭に立って指揮号令をした。
しかし、そんな絶頂期の田島を待っていたのが、大正9年(1920)3月15日の株式市場の大崩落、ガラ(株や商品相場などガラガラと暴落)である。7年11月に第一次大戦が休戦、翌8年6月ベルサイユ講和条約調印、それまでの戦争大好況の終焉である。生糸・綿糸・鉄鋼などの価格が三分の一から五分の一に暴落、船などの“一夜成金”が没落、会社倒産があいつぎ、銀行の取り付けや休業が起こり、日本紙器のメインバンク、七十四銀行も、このあおりで休業した。このとき日本紙器が株価操作をまかせていた兜町の証券会社・巴商会も、倒産した。大正10年2月、大設備投資で資金繰りがつかなくなり、輸入機械の操作にも手間取り、生産性は伸びず、低収益の上、大恐慌の勃発。田島は技術開発には天賦の才を発揮したが、経理は人まかせ、経営のバランス感覚には欠ける向きがあり、株価操作のための粉飾決算を知りながら、黙認していた星野錫社長の責任も問われ、大正10年2月1日、星の社長を始め、鳩山一郎取締役を除く、田島専務以下全役員は引責辞任し、万事を鳩山取締役に託したのである。(『日本紙業50年史』より)。その後いろいろいきさつはあったが、鳩山一郎社長以下、興銀から植田隆専務、安田から川崎清男常務(のち社長)が送り込まれ、十数年間の苦心惨憺ののち、昭和7年(1932)7月、借金を完済し、再建を完了したのである。

鳩山一郎
![画像:[浅野三兄弟]浅野鉢太郎](https://www.tokyo-shiki.co.jp/wp-content/themes/tokyo-shiki-new/assets/images/page/img_03_01.jpg)
[浅野三兄弟]
浅野鉢太郎
![画像:[浅野三兄弟]水野倶吉](https://www.tokyo-shiki.co.jp/wp-content/themes/tokyo-shiki-new/assets/images/page/img_03_02.jpg)
[浅野三兄弟]
水野倶吉
![画像:[浅野三兄弟]浅野鉄二](https://www.tokyo-shiki.co.jp/wp-content/themes/tokyo-shiki-new/assets/images/page/img_03_03.jpg)
[浅野三兄弟]
浅野鉄二
日本紙業発展の歴史の中で「日本紙器製造所」?「日本紙業株式会社」とは別に、もう一つの流れがある。それは木製抜型の創始に始まるルート、浅野三兄弟(浅野鉢太郎・水野倶吉・浅野鉄二)が起こした「尚山堂」と、そこから「東京紙器」-「凸版印刷」へ続くソフト重視の流れである。
幕末にドイツ人医師シーボルトから西洋医学を学び、わが国近代医学の父となった伊藤玄朴の孫に伊藤栄という人がいた。伊藤栄は明治に入り伊藤胡蝶園という化粧品製造会社の社長となった。白粉の成分である鉛白か鉛毒をおこすと騒がれたころ、無鉛を旗じるしに売り出された伊藤胡蝶園の御薗化粧料は一躍有名になり、たちまち化粧品界を支配した。
その伊藤胡蝶園へ化粧品用の紙箱を一手に納めていたのが四谷の「尚山堂」である。
浅野鉢太郎(1864-1910)・水野倶吉(1874-1923)・浅野鐵二(1878-1941)の三兄弟、水野倶吉は祖母の家を継いだので水野姓を名のっているが、この三兄弟の母が「尚山堂」のそもそもの産みの親、鎮(1841-1923)である。鎮は38歳で夫と死別、髪結いなどをしながら一家を支え、明治14年(1881)、子供たちを抱え、上京、四谷伊賀町に住まい、子供たちに木版や銅板の彫刻と印刷という手に職をつけさせ、「尚山堂」を起こさせた。
晩年は長唄、三味線を楽しみながら、大正12年83歳の長寿を全うして逝った。浅野家はその後、四代にわたって多くの家系を生み、現存者だけでも約150人、3年に1回、関係者が明治記念館に集まり、「孝行会」という集会を催し、親睦を図るほどの大一族である。
その源流として崇められているのが鎮である。三兄弟の長兄鉢太郎は尾張で木版彫刻家竹中章造の門弟となり、名工肌の天分を発揮、18歳のとき母に従って上京、尾州藩旧士族大沢氏の江川堂木版店の職人となり、30歳で母鎮とともに明治26年(1893)に四谷五郎兵衛町で独立、「尚山堂」を名乗った。
鉢太郎は努力家で、欧文の勉強から始め、和風木版から背景紋様の複雑な西洋木版へ、そして刀刻銅板へ移り、欧文名刺印刷をみずから創始した。宮内庁ほか諸官庁に認められ、大正天皇が皇太子時代の名刺や、大公使の名刺を頼まれるようになり、“名人鉢さん”の名をほしいままにしたが、明治43年に49歳で亡くなった。(『尚山堂概史』『浅野家史』より)。浅野鉢太郎が名工肌なら、次男水野倶吉は発明家・開発家で、事業肌であった。倶吉は12才で遠縁にあたる横内桂山の門弟となり、19歳まで銅板彫刻を学び、その後、現在の後楽園ドームのあたりにあった砲兵工廠に入った。明治27~8年の日清戦争のころである。彼は天分の開発精神を発揮し、銃の番号をいちいち手彫りではなく、自動刻印機で打ち込む方法を提案し採用された。砲兵工廠を退職後、明治32年(1899)、倶吉は砲兵工廠で知り合った小西六右衛門(小西六写真工業創始者)と兄鉢太郎の応援を得、四谷坂町で母とともに写真台紙の製造を始めた。事業家の倶吉は次第に仕事を伸ばし、明治35年には四谷区大番町(現新宿区大京町)に約200坪の敷地に工場を建てて移転した。このとき「兄弟三人が力を合わせてやろう」と事業を一本化、「合資会社尚山堂」と命名した。明治40年(1907)ごろ、尚山堂は米国から木工用糸鋸ミシン・刃材とその曲げ機・切断機など抜型製作用材と機器一式を約1万円で輸入、近代抜型製作に先鞭をつけた。
アイディアマンの倶吉は、次々に新機軸を生み出し、文字が浮き出る浮き上げ凹版印刷・エアブラシによる着色応用印刷・シール印刷・金箔型押し・日めくりカレンダー・箱もの・曲げものなどを世に送り出した。中でも特に有名なエピソードは、大正3年(1914)森永ミルクキャラメルの紙箱を倶吉が考案、上野公園で催されていた大正博覧会で、この紙製ポケット式キャラメルを20個入り10銭という缶入りの半分の値段で売り出したところ、飛ぶように売れ、森永のヒット商品となったことである。
またオフセット印刷機の輸入が杜絶したとき、ドイツのカタログを見ながらオフセット機国産第一号を開発したのも倶吉である。
大正6年(1917)、「尚山堂」は発展的に改称し、「東京紙器株式会社」となり、末弟の鐵二は長兄と次兄を援けてもっぱら管理面に腕をふるい、尚山堂の育成に貢献、尚山堂を母体に「東京紙器」が設立されると、常務取締役に就任した。鐵二は大正15年(1926)に「東京紙器」が「凸版印刷」に吸収合併されると、ひき続き凸版の常務として残り、昭和5年取締役、12年監査役となり、16年に現役のまま病歿した。(『尚山堂概史』『凸版印刷史』より)。最終的に合併することになる「尚山堂」?「凸版印刷」への流れは、ある日突然に起こったことではない。この二つには、もともと深いつながりがあった。凸版印刷の井上源之丞の義弟井口誠一は明治43年に尚山堂に入社、長い間倶吉の片腕として働いていた。そのことから、胡蝶園が「尚山堂」に化粧品容器を発注した際、すでに紙器部門を尚山堂、印刷部門は凸版印刷と仕事を分かち合っていた。森永製菓のキャラメルの外箱のときも、ポケット式外箱を考案し提唱したのは倶吉だが、その外箱(タトウ)の印刷は凸版、中箱(中舟)は尚山堂が担当した。
*【註】東京紙器株式会社
当社「東京紙器株式会社」と文中の同名の会社は別会社ですが、当社の設立には、文中にある浅野鐵二氏の長男浅野秀司氏のご協力とご支援をいただき設立した経緯があり、社名を引き継いだ形になっています。
Copyright ©2026 Tokyo-Shiki Co.,Ltd. All Rights Reserved.